人に期待することが優しさだとも言えますが、人に期待しないということも優しさだと思います。
人に期待されたい
多くの人は、周りに期待されていないということで、なにやら悲しいことのように感じてしまいます。期待されていないと感じると、やる気も湧いてこないので、何も手に付かないということも多いのではないでしょうか。きっと締め切り間近になれば、叱られるという負の動機づけによって、違う種類のやる気がうまれてきて、結局はやることになるのでしょうが。とても不思議な自己完結型の負のループです。
成果の前借り
人に期待されることがモチベーションにつながるということは成果の前借りです。第三者に期待されるということは、第三者からみても結果が成功になることが予想されると言うことです。さらに言えば第三者から結果が成功したら認めてもらえるというご褒美を思い浮かべて、その喜びを前借りしてモチベーションにつなげているのです。
成功をイメージをするというのは、一流スポーツ選手も行うイメージトレーニングに通じるものもあり、とても良いことです。成功までのイメージが具体的であるほど、脳も活発化して、不安が抑制されるという話もあります。周りから期待されることで、成功をイメージをするところまで思考をつなげれば正のループを手に入れることができます。
逆に、周りに期待されて成功をイメージしようとしてもイメージできないときは失敗の前借りです。実際には失敗していないのに何やら既に失敗しているような気持ちになります。褒めてもらえない、それどころか叱られるかもしれないと考えることでモチベーションが低下するのです。周りの期待が高すぎる場合には、失敗の前借りになる可能性が高くなります。マネージャーによっては、自分の基準を部下に押し付けることもあり、それはエゴの押し付けと言えます。マネージャーの基準は得てして高い期待になるので、部下を鼓舞するだけでなく、潰してしまうこともあります。成果の前借りとは所詮は借金なので、最終的に返せないとなれば利子を付けて請求されるものです。
モチベーションのための承認欲求の危険さ
期待しないのも良くないし、期待が高すぎても良くないとなると丁度よい期待をかけるしかないということになります。マネージャーであれば丁度よい期待をかけてあげられるべきだというのはそのとおりですが、これは非常に難しいことです。
周りに期待されるかどうかで、モチベーションが変わるということは、承認欲求が動機になっています。丁度よく期待をかけるということは良いことですが、承認欲求を軸にしたモチベーションのコントロールはどこかで限界にぶち当たります。期待という成果の前借りをしなければ、やる気が起きないという根本的な問題に目を向ける必要があります。これはマネージャー側もそうですが、部下の方もここからの脱却が必要です。
ラディカル・アクセプタンスという心理学の考え方があります。ありのままの事実を受け入れるということです。周りの期待も、部下のモチベーションもコントロールできるものではありません。コントロールできないものに一喜一憂するのではなく、ここから自分に何ができるのかを考えるべきです。
また、老子の言葉に、大国を治むるは、小鮮を烹るがごとし、があります。マネージャーの心構えとして忘れては行けない言葉です。
いい意味で、期待を裏切ろう
マネージャーのエゴで期待されるぐらいであれば、期待されない方が楽です。周りからの期待の有無にかかわらず、期待をモチベーションにすることが前借りに過ぎないということに自覚することが大事です。それよりも、自分の成果を自己評価すること、成果を提供して使ってくれるユーザーからのフィードバックを大事にするという基本に戻ることが必要です。
周りの評価に関心がある人は、期待に応えようという気持ちが強すぎるのかもしれませんね。期待に応えようという気持ちも大事ですが、無理に合わせ過ぎることで自分を見失うことにもなりかねません。適度に期待を裏切ることも大事です。
このように自律しようとしている人に対する接し方として、期待をかけるということが本当に優しさなのか。期待をかけるかけないではなく、暖かく見守るスタンスと結果に対して的確にフィードバックする方が本当の優しさなのではないでしょうか。







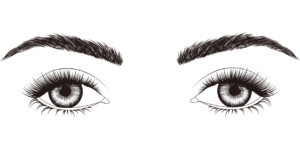



コメント
コメント一覧 (3件)
期待とは一種の支配であるともいえます。
人は多かれ少なかれ期待という名の支配を喜びと感じるものです。
どちらの観点からもある優しさ。簡単に結末をつけられないからとても難しいですね。
だからこそ、自分と向き合ったり自分を受け入れることでの、1歩先があるように思えました。
色んな観点でのマネジメント(階層別、業務別)を経験した事がある方はあるんじゃないでしょうか。
または、同僚やマネジメントを担っている部下から「あいつには期待していたのが残念・・・」
または部下から、「こんなに頑張っているのにウチの上司は褒めてくれない・・・」など
居酒屋でも聞こえてくる様な会話ですが。
記事の様な事が1つでも思い当たるときは、フィードバックも受け入れれず視野が狭くなっているのかもしれません。
この記事にあったスタンスができる様になるには、期待と理想のギャップからまずは自分と向き合い、そのギャップに素直になれることから始めていける人になれたらいいなと思えました。
このギャップに素直になれるかどうかで責任者として器の成長機会にもなるだろうし、部下は良い意味で期待を外してギャップの中から、褒められる以外のモチベーションが見つけることができるかもしれません。
プロジェクトやチームの初めは期待がゴールではないのですが、いつの間にかそうなっている時がありますね。
改めて問いたいです。
”期待”という概念で、自分や相手を動かしていませんか?
”期待”と言いながら、マイクロマネージメントしていませんか?されていませんか?
“期待”という言葉をかけながらも、共に汗を流してくれたり、一緒に考えてくれていますか?
仕事は生活時間の大半を占めており、最初は人間関係が浅いままで仕事の時間は人間関係を構築するより早く進むものです。
もちろん、期待されていることや期待することが悪いわけではないですが、結末がしょうもなく期待で終わるような始末であれば、
期待だけで終わらせないアウトプットができる様になると仕事の中身も濃いものになるに違いないです。
そして、これが解るようになってくると、顧客志向に優れたマーケッターにもなるでしょう。
私はこの記事を読みながら、この話はクライアントとの関係性の中にもあるものだと感じ、抽象的に捉えると、自身への期待と現実のギャップが根幹にあるのではと考えていました。
なぜなら、周りからの期待や誰か(何か)への期待は全て自身のフィルターを通しているからです。
このギャップに苦しむ人は、自身との対話を通して解消していくところからなんだろうなと思います。
「このように自律しようとしている人に対する接し方として、期待をかけるということが本当に優しさなのか。期待をかけるかけないではなく、暖かく見守るスタンスと結果に対して的確にフィードバックする方が本当の優しさなのではないでしょうか。」
それが出来ている人は、期待をされた時の受け取り方も異なるだろうし、誰かに期待するときに自分が想定しているものを押し付けず優しく見守りながらも相手との対話もできるのだろうなと感じています。